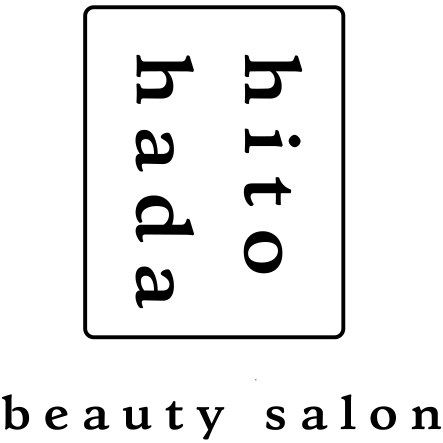寒い時期はもちろん増えるかと思いますが、人によって夏にも引きおこる「冷え性」。冷え性は肩こり・腰痛・便秘・不眠など、いろいろな不調を引き起こすと言われており、多くの方が悩んでいるでしょう。
その「冷え性」ですが、お肌にも影響を与えているのを可能性がございます。今回は、冷え性とお肌の関係や、冷え性になる原因・対策をご紹介いたします。
冷え性からくるトラブル
・くすみ・シミ・肌荒れ
血行不良により新陳代謝が滞ると、お肌に古い角質が残りやすくなります。これはくすみやシミの原因になり、さらにニキビや吹き出物を発生させることもあります。
・ターンオーバーの乱れ
冷え性で血行が悪くなると、身体中に酸素・栄養素が行き届かなくなります。これはお肌も同じです。お肌に必要な酸素・栄養が行き届かず、表皮の生まれ変わりが起こりにくくなってしまうのです。
血行不良はターンオーバーの機能も低下させてしまうので、古くなった角質がいつまでもお肌に残ってしまいます。新陳代謝の悪化による「角質肥厚」が、垢のようなゴワつき・ザラつきを引き起こす原因となってしまいます。
・お肌の乾燥
新陳代謝が滞ると、お肌のバリア機能も低下してしまいます。バリア機能の低下はお肌の乾燥につながります。
またお肌の乾燥はシミやむくみに繋がっていきます。
なぜ冷え性になるのか
・筋力の低下
身体の熱は筋肉が作っているのをご存じでしょうか?筋肉を動かすときにはエネルギーが必要ですがそのエネルギーを産生する際に熱が発生します。
筋肉が増えると体が冷えにくくなり、収縮することによってポンプのように血液を循環させているので、筋肉が増えると血流が良くなります。
逆に筋肉が衰えると代謝も落ち、血行が滞ります。血行が滞るということは、体の末端まで血液が行きにくくなるため、手足が冷えやすくなるのです。
男性より女性のほうが冷えやすく、これは筋肉量が関係しています。女性は男性に比べ筋肉量が少ないため、作り出される熱量が少ない上にポンプの力が弱くなり、体が冷えやすくなります。
また加齢とともに冷えを感じやすくなるのも筋肉が衰えるためです。脂肪は一度冷えると温まりにくい性質を持っている為、男性に比べて筋肉が少なく脂肪がつきやすいという点でも、女性は冷え症になりやすいと言われています。
・自立神経の乱れ
自律神経は体内の内臓機能をコントロールする重要ま機能であり体温調節にも影響を及ぼしています。自律神経がうまく働かずに乱れてしまうと、冬はもちろん、夏でもカラダの冷えが常態化してしまいます。
また、腸の運動も自律神経によって左右されています。そのため、自律神経が乱れると下痢・便秘も起きやすくなり、基礎代謝も低下してしまい、やがて冷え症へ繋がってしまいます。
女性の体は女性ホルモンの増減があり、女性ホルモン・自律神経はお互いに影響を受けやすく、どちらかのバランスが乱れると、もう一方のバランスも乱れやすくなります。
ストレスで月経周期が乱れたり、更年期に自律神経失調症状が現れたりする女性は、男性よりも冷え性になりやすいと言えます。「生理中は体が冷えやすい」「冷えにより生理痛がひどくなる」という方もいます。
女性ホルモンの量がぐんと減る更年期には、冷えがひどくなるという方が多くなります。
・生活習慣の乱れ
生活習慣が乱れることも冷えの原因になります。甘いものを食べ過ぎていたり、過度なダイエットなどにより栄養バランスが偏った食習慣が続いてしまうと、ミネラルやビタミン不足になりやすく血行不良につながります。